スポンサーサイト
上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。
新しい記事を書く事で広告が消せます。
熊本県熊本市に在住ながらも、仕事ではあっちこっちに出回っています。たまに心理臨床的なことも書きますが、中心はドライブの記録や日々の雑感です。
| 鳩山由起夫首相のツルの一声で、厚生労働省は瞑想や催眠療法といった民間医療に加え、チベット医学、ホメオパシーなど世界各国の伝統医学の保険適用や資格 制度化をマジメに考え始めた。 |





| 原口一博総務相は5日の自殺総合対策会議で、うつ基本法とひきもこり基本法の制定に向けて検討を始めるべきだと提案した。 |


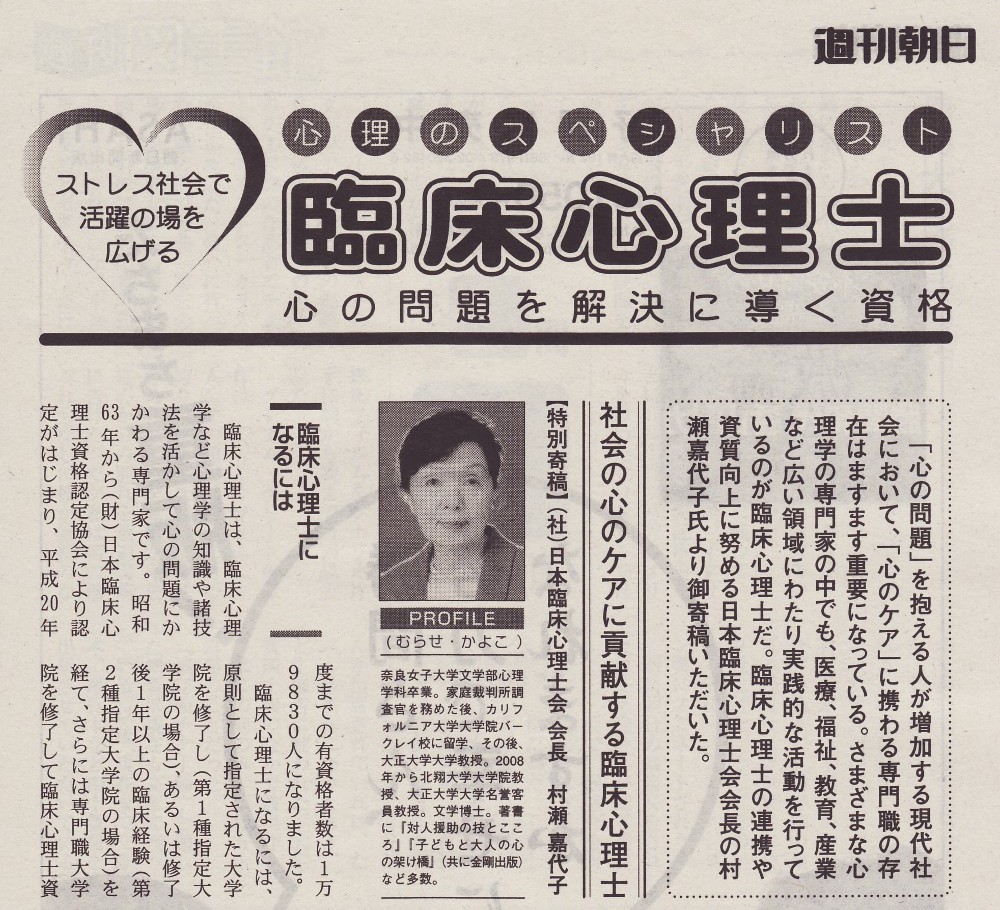

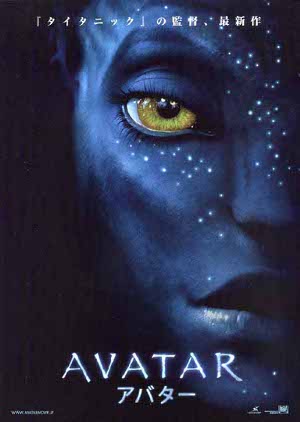
| 厚生労働省は、出産前後のハイリスクな治療にあたる総合周産期母子医 療センターが、母体の脳血管障害など産科以外の救急疾患にも対応することなどを盛り込んだ新たな整備指針を策定し、27日までに都道府県に通知した。 (中略) 確保すべき職員として麻酔科医や臨床心理士、長期入院児を支援する コーディネーターを挙げた。 |